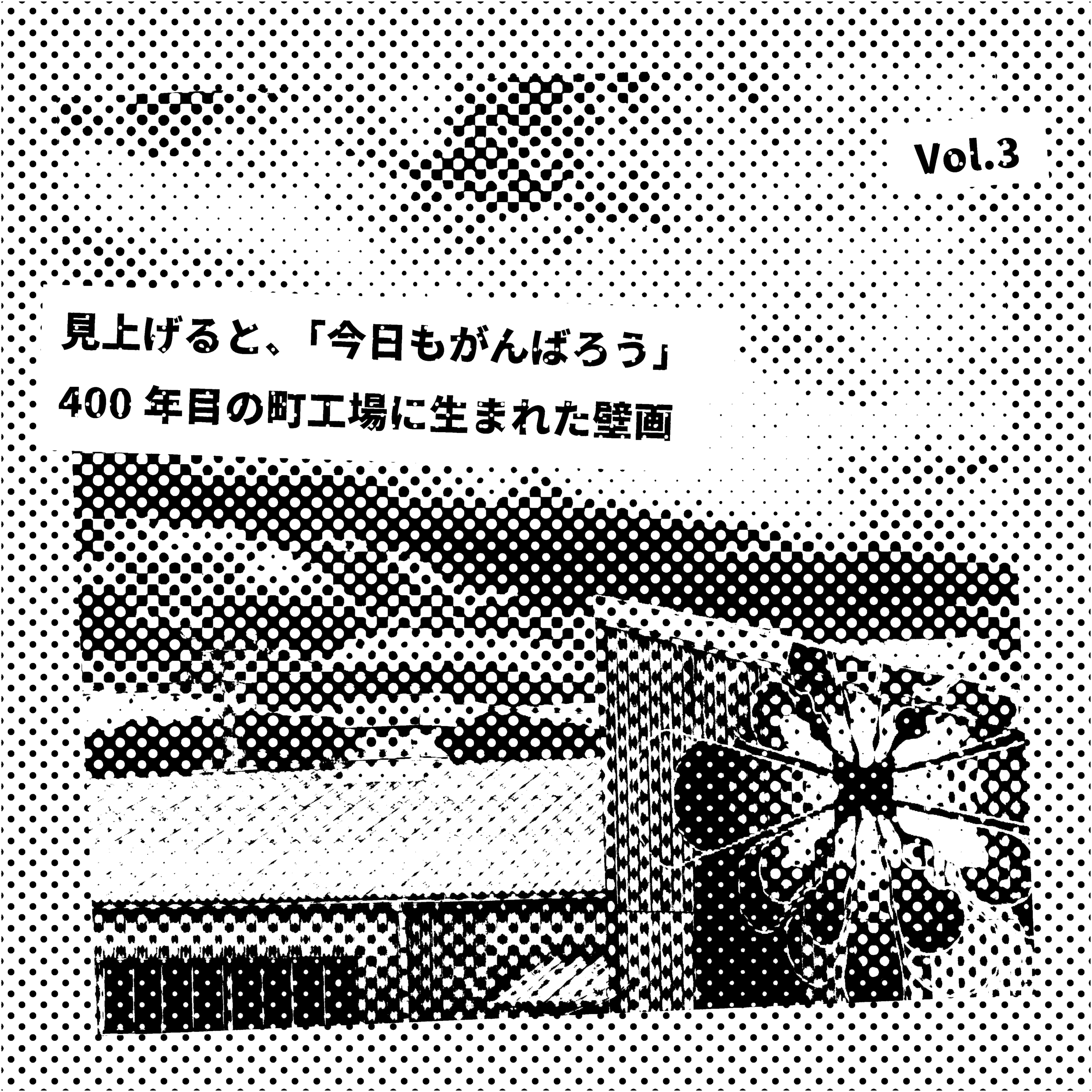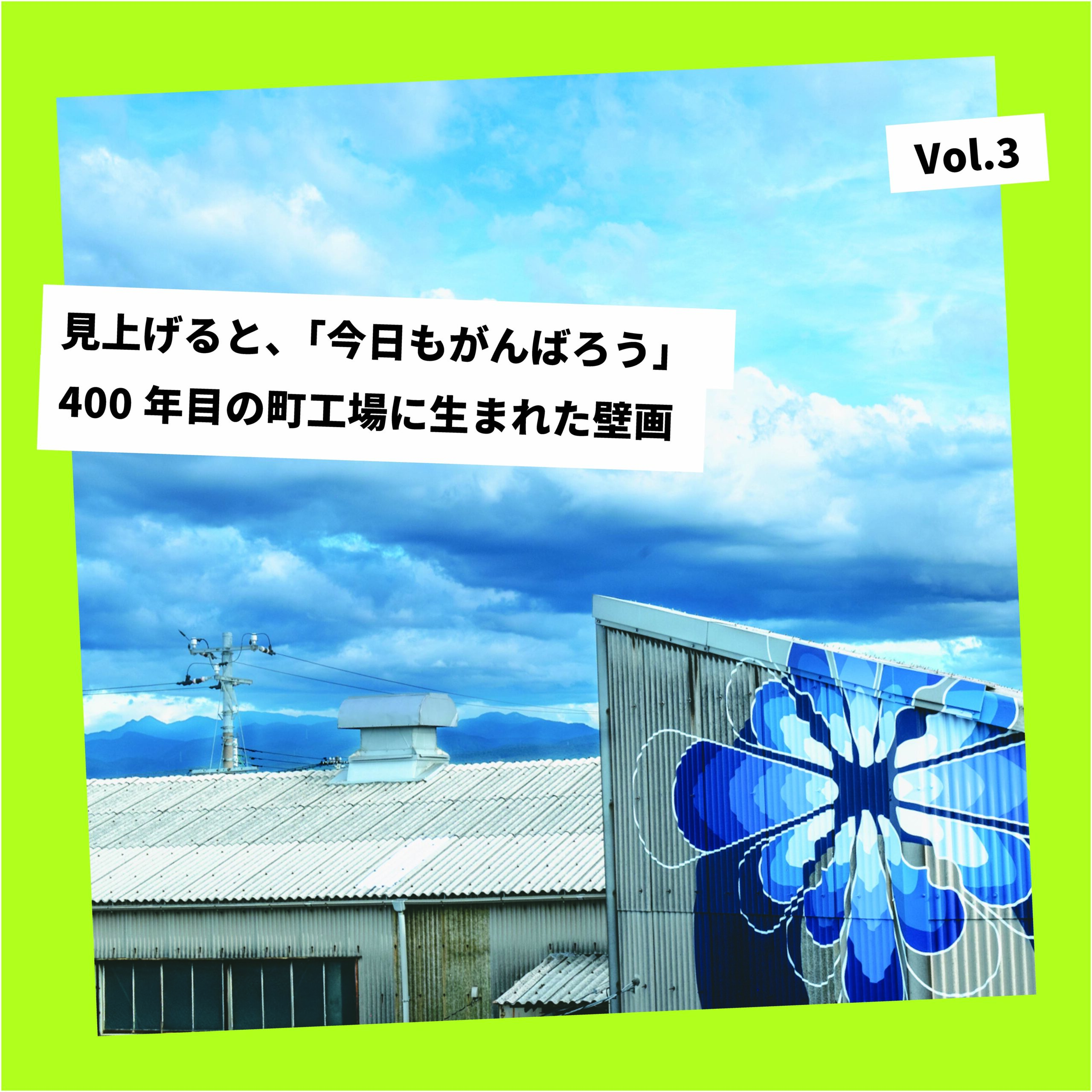大自然に少しフィクショナルなエッセンスを加えて、独自の世界を描き出す墨絵アーティスト、菅原ありあさん。最新の個展では表具店と協力してミニ掛け軸の制作を行うなど、新たなアプローチで伝統文化の魅力を惹き出している。一体何が彼女を、自由な挑戦へとかき立てるのか。その意欲の源泉をたどった先にあったのは、「良いものはなるべく自分の生活に取り入れたい」という素朴で強い想いだった。
墨絵を描くことは、瞑想のようなもの
ーありあさんは、どのような経緯で墨絵を始めたのでしょうか。
もともと水彩画を描いていたのですが、あるとき、紙の質にもしっかりこだわりたくなったんです。で、和紙を使おうと思ったときに、それに合うのは墨かなと。
ーキャンバスを和紙に替えたことがきっかけだったんですね。
はい。でもやっぱり墨絵は“伝統文化”というイメージが強くて。私、父がアメリカ人で私自身もアメリカで育ったんです。日本の伝統文化にあまり触れられていなかったので、そんな自分が墨絵を始めていいのかなという思いもあり、なかなか挑戦できずにいました。でも当時はまだ誰に見せるつもりでもなかったですし、個人で挑戦する分にはいいかなって。勇気を出して試してみたら、和紙に触れた瞬間の墨の広がり方がすごく美しかったんです。
ーそこから墨絵の魅力にはまっていったと。
墨って、種類によって赤色に見えたり青色に見えたりするのですが、水彩絵具にはない厚みと色味が、とても好みでした。あとあの独特な匂いも、なんだか気持ちを落ち着かせてくれます。墨絵を描いている時間は、私にとって瞑想のような時間でもあるんです。

色味など視覚的な魅力だけでなく、作品作りを通して自分自身の精神状態を整えてくれる墨絵に、「(求めていたもの)すべてがはまった」という
ー古典的な水墨画とはまた違った入口から入られたかと思いますが、作品を作る上で、ご自身でも何か意識はされているのでしょうか。
いわゆる伝統文化としての墨絵とは違うものを描いてしまっているなあというのは感じていましたね。だから、周りの目も最初は少し気になりました。でも、自分の描きたいものだけ描こうと、それだけは決めていました。

2024年9月に行われた個展会場にて。作品のインスピレーションは自然から得ることが多い。真っ白な壁を見てぱっと浮かんだ風景をそのまま絵にすることもあれば、外を歩いているときに瞬間的に見えた風景を切り取ることも
部屋に飾りたくなる掛け軸を、作りたかった
ー今回の個展では、掛け軸にして飾られた作品も多くみられますね。
最初の個展では、作品を全部ガラスケースに入れて展示したんです。でもガラスの枠だと、どうしても反射してしまう。和紙の質感とか墨の広がり方とか、もう少し絵の繊細なニュアンスが伝わる展示方法がないか探した結果、掛け軸にたどり着きました。掛け軸って本当によく考えられているんですよ。作品が綺麗に見えるだけでなく、運びやすいし、保管しやすい。軸棒が風に当たって揺らぐ感じもすごく素敵で、好きなポイントがたくさんありました。
ーなかにはとても小さなサイズのものもありますよね。スタイリッシュかつどこか現代的なデザインで、掛け軸のイメージが覆されました。
こんなに素晴らしい技術なのに、何でこれまで掛け軸のことをあまり知らなかったんだろうって考えてみたんです。そしたらやっぱり、家の環境かなって。床の間とか和室がない家では、どうしても飾りにくいですよね。じいちゃんばあちゃんの家に行くと飾ってあるけど、私たちの世代からするとやっぱり距離を感じてしまう。それはもったいない!と思いました。で、どうやったら掛け軸の魅力をみんなに伝えられるか考えたときに、サイズが小さい、ミニ掛け軸なら簡単に飾れるし、可愛いかなあって。もともと個人的に小さなものに心惹かれるのもあるんですけど(笑)。

「自分の部屋に飾りたくなる」を大事な基準に、サイズやデザイン、色味など全てこだわった
ーこのサイズの掛け軸を作ってもらうってなかなか大変では?
苦戦しましたね。そもそも掛け軸って規格が決まっているんです。今回の作品のように小さなサイズの掛け軸を作るなら、全部一(いち)から特注するしかありません。それを引き受けて下さる職人さんがなかなか見つからなくて。一緒にお仕事してくださる方を見つけるまでにいろいろな表具店に足を運んだのですが、センチじゃなくて“寸”でサイズを測るとか、そういった基本的なところからカルチャーショックばかり。掛け軸について知れば知るほど、長い伝統があるにもかかわらず外部からやってきた自分が新しい試みを行おうとしていることに対して、不安になることもありました。
やってみないとわからない!諦めない思いがコラボを実現
ーそして、ついに一緒にやってくれる表具店を見つけたと。
はい、都内の表具店さんが引き受けてくださいました。これはもう無理かもしれないと思っていたところだったので、すごくありがたい気持ちでしたね。2代目表具師の小鍋篤志さんが「掛け軸が長く続いてほしいから、若い世代がこうやって掛け軸に興味を持ってくれるのはうれしい」と、私の想いを前向きに受け止めてくださったんです。
ーありあさんと表具店。分野は違えど、同じ“ものづくり”に携わられているという共通項があるかと思いますが、一緒にお仕事をしてみていかがでしたか?
実はお願いできる表具店さんが見つからなかったときに、独学で作れないか挑戦してみたことがあったんですけど、「裏打ち」という作品の裏側にもう一枚紙を重ねて貼り付ける作業とか、本当に難しくて。その経験があったので、本当にすごいなあと思いましたね。小鍋さん含めスタッフさんは皆、失敗が許されない局面でも素早く正確に作業を進められるんです。精神面での強さもそうですし、その技術に圧倒されました。小鍋さんの表具店は普段、文化財の修復なども行っています。一点ものを取り扱う緊張感を常に抱いてお仕事されているからこそ、成せる技なのだと思いました。

<制作時の風景1>小鍋さん(右)と。1代目の父から伝統を受け継ぎつつ、今回のように同世代や若い世代を巻き込んだ新しい挑戦をしていきたいという

<制作時の風景2>軸棒取付け前のミニ掛け軸。サイズが小さいだけでなく通常より薄い和紙を用いて作られたため、破れたりにじんだりするリスクもあったとか

<制作時の風景3>通常の掛け軸制作とは一味違う、今回の依頼。「手が震えますよ」と笑いながらも、頼もしい手つきで作業を進める小鍋さん

<制作時の風景4>RE/SAUCE Project直営の拠(よりどころ)「すギ留」に飾る掛け軸も準備中。コーヒー豆の木をモチーフにしたいというオーダーに、「枝からコーヒーの液体が垂れてくる」という彼女らしい解釈を加えて応えてくれた
良いと感じたものは生活に取り入れたい。ただ、それだけ
ー掛け軸の制作を終えて、次のステップへの手応えは感じましたか?
勇気を出して声をかけてみれば実現することもある、ということは実感を持って知ることができました。これからも、聞いてみないとわかんないじゃん!というマインドを大切に(笑)、職人さんの力もお借りしながら挑戦を続けていきたいなと思います。

「今回の個展では、自分が思い描いていた世界が見た人に届いたと感じる瞬間がたくさんありました。それがすごくうれしかったです」とありあさん
ー今後の活動にもますます期待が高まります。掛け軸への挑戦はまだまだ続く予定でしょうか?
そうですね。今回の個展で、若い人からご年配の方まで、男性女性問わず本当に幅広い年代の方が掛け軸を購入してくれたんです。掛け軸に対するイメージをある意味リフレッシュするような作品になれたのならうれしいなと思いますし、皆さんと掛け軸との距離を縮められるような作品をこれからも作っていきたいですね。たまにふと、こんな自由なことしちゃってていいのかな?と思うこともあるのですが、でもやっぱり私は墨を使って絵を描くのが好き。素晴らしい文化だからこそ、素晴らしいものは自分の作品づくりや生活に積極的に取り入れたいなと思うんです。なるべく自分の近くに置いておきたいというか。ある意味欲張りなのかもしれません(笑)
ー伝統を「のこす」「受け継ぐ」というと壮大なミッションのように感じられますが、ありあさんの場合は、良いものを生活に取り入れたいというあくまでも自然な動機から来ているんですね。
少し気分を上げたいときに、いつもよりちょっといいカフェオレを飲んで仕事を始めることとか、ありますよね。自分が好きなものや価値を感じるものを生活に取り入れると、幸せを感じることは、実はみんなもう気づいてる。だから、自分が素敵だなと思ったことをどうしたら生活に取り入れられるか考えることが幸福につながるのかなと思っています。私にとってはその一つが、墨絵や掛け軸。自分が価値を見出しているからこそ、みなさんにとってもそれらが身近になればいいなという願いも込めて、活動を続けていきたいですね。
RE/SAUCE Project直営の拠「すギ留」は今年2月26日にオープン。コーヒー豆の木をテーマにしたオリジナル掛け軸を、お見逃しなく。
プラン・コーディネーション:カトー
取材・執筆:齊藤葉(都恋堂)