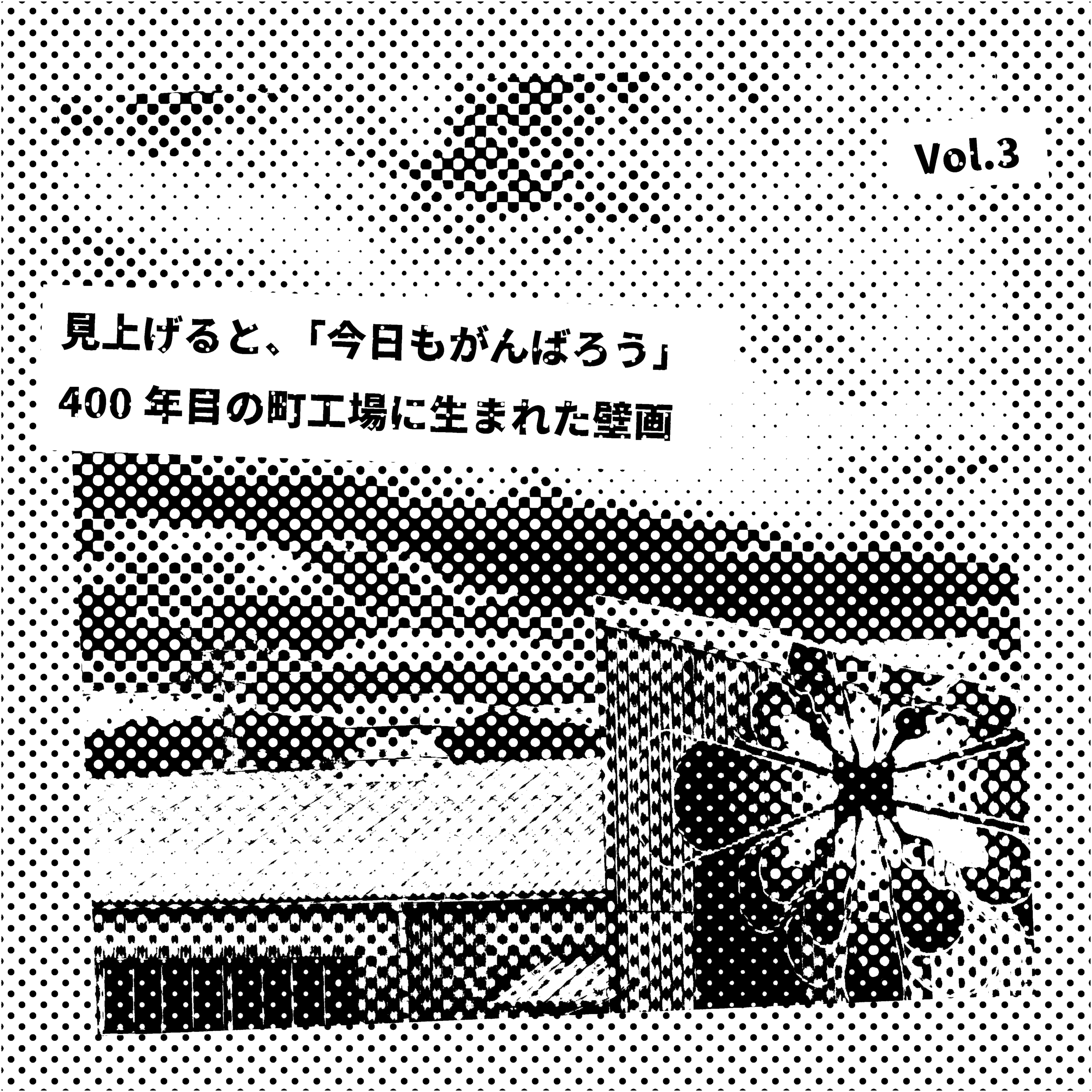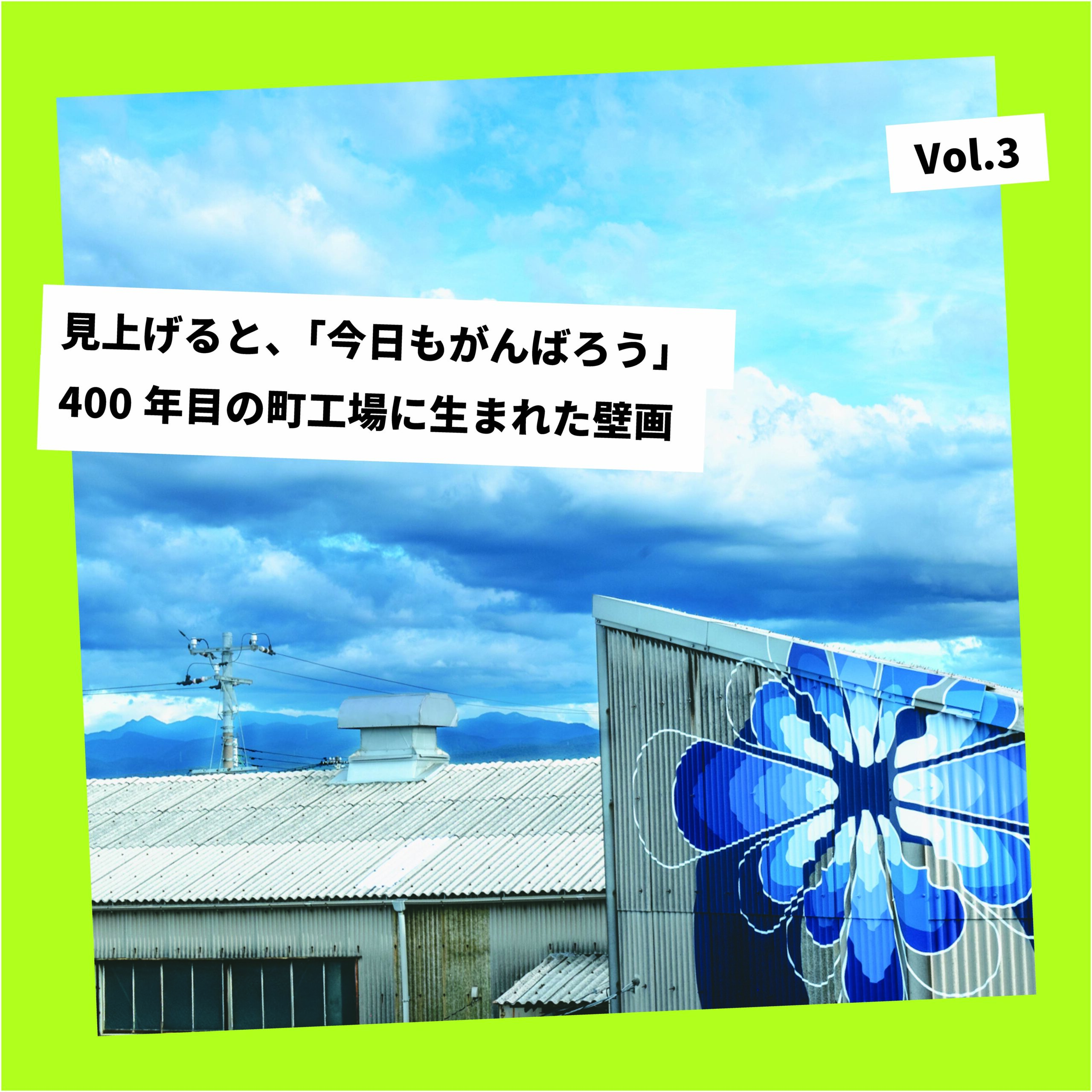陶芸ブランド「ONE KILN」×
雨のパレード 福永浩平
今回は、城戸さんがRE/SAUCE Projectの活動理念に深い共感を示してくれたことにより、アトリエへの訪問が実現した。訪れるのは、同じく鹿児島出身であり、かねてよりONE KILNの作品世界に惹かれていた福永浩平(バンド「雨のパレード」メンバー)。音楽のジャンルやバンドという形態の枠にとらわれない、独自の世界観を提案し続けている。
器と音楽、一見異なる立場の二人が共鳴する“ものづくり”の魂とは?
「桜島が大好き」なふたりをつなげた器
福永:
僕、「ONE KILN」のAsh(アッシュ)シリーズの器とは、東京で出会ったんです。もう好みのドンピシャで、見ると「鹿児島」と書いてある。それも、火山灰を釉薬に混ぜることでこの質感が出ていると。僕、鹿児島出身で桜島も大好きだからすっごく嬉しくて、ずっとお会いしたかったんです。
城戸:
ありがとうございます。桜島、みんな好きですよね(笑)。

ONE KILNの代表作ともいえるAshシリーズ。桜島の火山灰を調合した釉薬(ゆうやく)※を、ひとつひとつ刷毛目で塗って焼成されている
※釉薬…素焼(すやき)の陶磁器の表面に光沢を出し、また、液体のしみ込むのを防ぐのに用いるガラス質の粉末
福永:城戸さんが陶芸を始めたのは、いつですか?
城戸:鹿児島の高校卒業後、東京のデザインの専門学校に進み、設計事務所で働いていたんです。そこで、いろんなデザインをやりながら、陶芸家になりたいと思うようになったのが、24歳の時です。
福永:おお、デザインから始まったんですね。
城戸:当時は、陶芸を職業にするには、職業訓練校行くか、大学に入り直すか、弟子入りするかの三択で、どうにも入り口が見つからない。最後の最後に、設計事務所時代のつてで、佐賀県有田焼の窯元を紹介してもらい、陶芸の世界へ入ったんです。まわりの友達は、有田で陶芸をやると言うと「仙人になるのか!?」と(笑)。でも僕は、最初から今のようなブランドを作ろうという意識がありました。
福永:「ONE KILN」のスタートはどんなふうに?
城戸:2008年に佐賀から地元に帰り、小さなガレージで僕一人で始めました。何々焼きっていう伝統を引き継いではいませんが、有田で修行して学んだ型の技法がベースになっています。
福永:型を作って、そこに土を流し込むんですよね。形が同じ陶器でも独自の釉薬をかけることで、ひとつひとつランダム性が出て、どれも表情が違う。ろくろより効率良く作ることができて、ビジネスのシステムとしてもすごくいいなと思いました。釉薬をどうやって発想したかを、めちゃくちゃ知りたいです。

粘土と水を混ぜ合わせた泥漿(でいしょう)と呼ばれる液体を流し込み、成形する
逆転の発想で、天敵の厄介者を生かしてみた
城戸:地元に帰った時、この土地の素材でしかできないことをやりたいと思っていたんです。有田焼は泉山陶石という土が取れる場所に窯元が集まって生まれたんですが、今、原料になっているのは熊本の天草陶石がほとんど。有田で焼いてはいるけど、土は熊本なんです。僕がここ鹿児島でしっかり地元に根ざしたものを作るなら、やっぱり桜島を活かさない手はないかなと(笑)。火山灰は厄介者だけどみんな大好きですから。ただ白磁にとっては、灰は天敵。白磁が灰で汚れてしまうから、鹿児島は磁器の白磁の製作には適さないと言われていたんです。でも僕は白磁の技法しか学んでこなかったので、どうすれば鹿児島に適用するかなと思った時に、火山灰を生かそうと。
福永:お〜!逆転の発想だ。
城戸:釉薬に火山灰を混ぜ、黒い器に仕上げるなら、灰がついていても全然影響ないですから。
福永:それでこの七色のような不思議な色合いに?

色味は窯の中に置く位置や、釉薬の化学反応によって絶妙に異なるため、全て番号で管理している
城戸:これは火山灰だけの影響じゃないんです。始めは単純に火山灰を土に塗って焼いてみたんですよ。するとゴツゴツザラザラして見た目も使い勝手も良くない。火山灰といろんな鉄分(鉱物)を0.1g単位で調合し、テストピースを作って、その中から「この色が一番きれい」と見つけたブレンドです。灰プラス鉄分のレシピですね。
福永:レシピがあるから仕上がりがある程度均等になるのかぁ。
城戸:それが同じレシピでも、100個、窯に入れるとお互いが反応し合って全然違う色になるんです。いろんな要因がわかるまで、5年ぐらいかかりましたね。火山灰を使用していると言うと、「SDGsですね」と言われますが、そういう意識ではなくて、たまたま火山灰が邪魔してくるから混ぜてみようという好奇心、それと5年の研究でできものです(笑)。
果たして、音楽の世界にもレシピはあるのか?
福永:レシピで言うと、音楽も似たところがあって、僕にも10年かけて創ったレシピがあります。レシピが何かを言語化するのは難しいんだけど、自分の琴線に触れるか触れないか。その琴線の感覚は10年で鋭くなっているような気がします。
城戸:僕、フェスで「雨のパレード」を聴いて、めちゃくちゃ感動したんですよ。全身に何か浴びているような感覚になって。でも、あの歌詞と音、リズム、主旋律のレシピがあれば、いつでもどこでも「雨パレ」になるかというと、きっとそうじゃない。その都度、絶妙に音の大きさを変えたり、福永さんの繊細なこだわりがいっぱい詰まってるんだろうなって。

会話がはずむ2人
福永:わ〜嬉しいな。僕は音楽でもグッズ製作でもそうなんですが、自分の名前で出すんだったら、自分が一番いいと思える形で出したい。だから、良くも悪くも自分でやっちゃうことが多いんですよ。以前は、大人の言うことを聞いたら、売れるのかな?と思った時期もあったんです。でも先人の手法が今も響くとは限らないし、誰かの意見を取り入れて作ったものを、好きだと言ってくれる人がいても、「えっ本当に!?」って逆に戸惑ってしまうというか。不健康ですよね。
城戸:わははは〜。そうなんですね。
福永:だったら、自分が納得いくものを出して、良し悪し言われたほうが気持ちがいい。そういう意味では、今は作家寄りの気分になっているんですが、城戸さんはいかがですか?
一人で創るアーティストと皆で創る陶芸家。作家性とは何か?
城戸:僕も最初の頃は、作家性を出そうと思って、誰にもできない表現、自分にしかできない形を求めて、一点ものの花瓶とかを作っていたんですよ。でも、結婚して子供が生まれ、食卓で並ぶのは僕の器じゃなかった時に、あれ…?と思って(笑)。そこから尖ったものじゃなく、日常の食卓ですっと手にとれるものがいいよなと。作家性はここで出す、ここではいらないと線を引くようになりましたね。

ONE KILNのブランドフィロソフィは、「THE SUN TO A TABLE – 食卓に太陽を -」

コーヒードリッパー。ざらつきのある手触り、深みのある色が落ち着く空間を作り出す
福永:家族の食卓で気づくことがあったんですね。ブランドとしてはどうですか?
城戸:スタッフと分業制だから、続けられているところが大きいですよね。もしこのお皿が良いねとなった時、年間1000枚、2000枚を作らないといけない。ずっと作家の気持ちではできないところもあって。
福永:確かに。
城戸:まわりに頼りながらだと、自分の中に芽生えたこと(アイデア)にも焦点を合わせられるし、金継ぎのシリーズ「ONE KILN Reproduction」なんかは、スタッフのおかげで実現できたシリーズですから。
福永:金継ぎ、すごく素敵ですよね。どんな経緯で生まれたんですか?
城戸:始まりは、製作途中で割れた作品もどうにか循環させたいという、僕のもったいない精神です。窯の中での割れ方って、落として割れるのとは違い、ちょっと面白いんですよ。貫入と言って、冷めてる最中に、ぴきん!と割れるんだけど、ひびが途中で止まっていたり、裂けるように割れていたり。これは一種のアートだ、リプロダクトしたいと思っていたところ、スタッフのサトミちゃんが、金継ぎ教室に通ってくれて形になりました。

偶然生まれたひび割れが、美しい個性になる
福永:もうその発想がアートですよね。あと感じるのは、サトミちゃんはじめ、すごく陶芸が身近に感じられるアトリエだということ。作家として、またチームとして、今後やってみたいことってありますか?
陶芸をもっと身近に。バンドマンはもっとつながれるように
城戸:陶芸の世界の間口を広げたいですね。まずは僕の工房が、町のパン屋さんみたいに主婦や高校生がバイトに来られるような場で、誰もが陶芸と接点を持てたらいいなと。伝統的な窯元の技と、陶芸に興味がある人との間の立ち位置にいるようなブランドでありたいです。福永さんはいかがですか?
福永:そうだなあ。音楽の世界も特殊で、どのバンドも独自に進化していくんですよ。曲作りもライブやリハまで、それぞれのやり方があって、アーティスト同士がからむこともあまりないんです。そこをつなげられるシステムができたらオモロいなって。たとえば、先輩バンドがメンター的に新人バンドにレコーディングを見せたり、うちはこうやって曲を作ってるよとオープンにするような仕組みが作れたらって。
城戸:面白そうですね。僕も佐賀にいた頃は周りには焼き物作家しかいなかったんですが、鹿児島では、木工作家さんはじめいろんな作家と出会って刺激されることが多いんですよ。
福永:何かを“つくる”者同士の交流って発見があってすごく大事だと思いました。城戸さんとの出会いもまさにそう。ありがとうございました。
城戸:こちらこそ、楽しかったです。
取材を通して、ものづくりに対する逡巡や想いを共有しあった2人。「何か一緒にできたら…」というひょんな話から、コラボレーションプロダクトの制作が決定! 福永さんが監修し、ONE KILNが制作を行うオリジナルプランターが登場する。


数量限定で、福永さんが多肉植物を植え込んだスペシャルVer.も販売予定
完成したプロダクトは、RE/SAUCE Project直営のカフェ「すギ留」にて、4月19日(土)〜4月27日(日)※までの期間限定POP-UPにて販売予定だ。
さらにプロダクトの販売記念として4月19日(土)には城戸さんと福永さんのリアル対談イベントを開催。ものづくりの新天地を切り開く2人の熱いセッションをぜひ、現地にて。
▼イベントの参加申し込みはこちらから(4月9日(水)申し込み開始・先着順)
https://rmvs.re-sauce.jp/products/onekiln
※4月21、22日はお休みさせていただきます。
※POP-UPおよび対談イベントの詳細は、「すギ留」および「RE/SAUCE Project」公式インスタグラムにて順次お知らせいたします。参加ご希望の方はもれなくチェックを!
取材・プラン:HAL.カトー
コーディネーション:清水隆司(Judd.)
執筆:くればやしよしえ