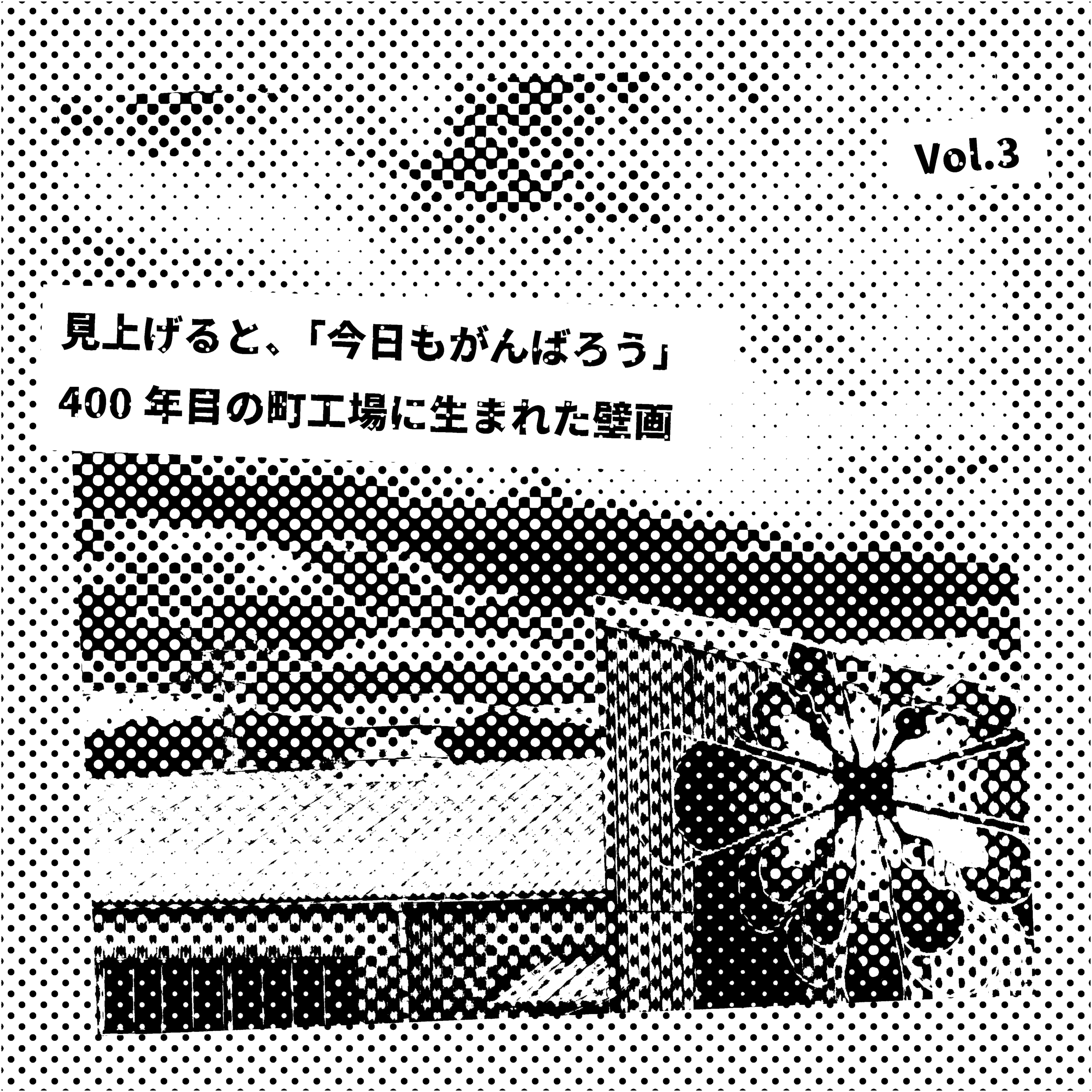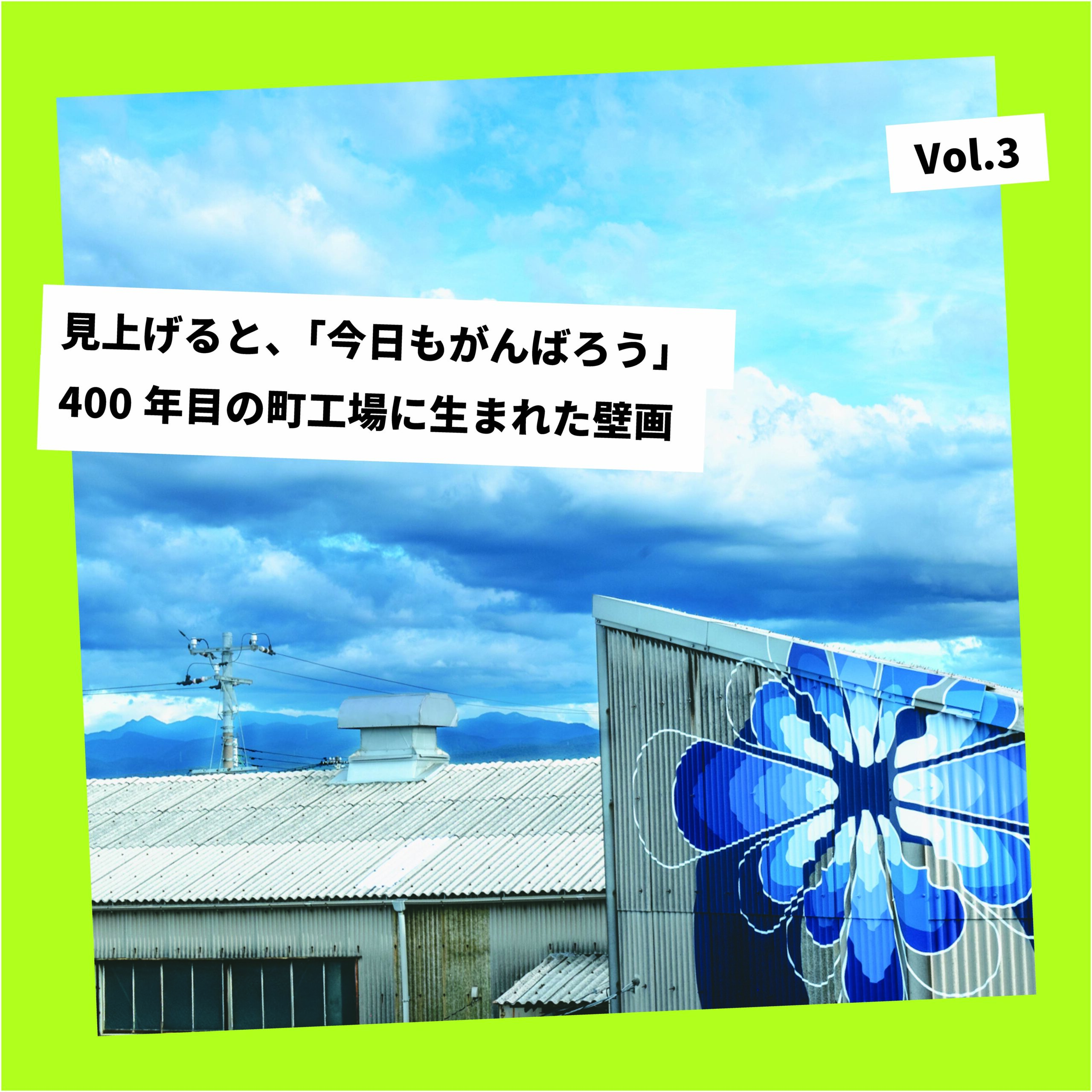武士珈琲の旅 by おさむらいさん vol.2〜珈琲の生まれる土地、ギターが育つ土地〜
日本のコーヒーは美味しい。正確に言えば、世界から厳選されて輸入された生豆を日本の技術で焙煎し、完成したコーヒーが美味しい、のだ。順を追って話してみよう。
まず、コーヒーには三大原種と呼ばれる原種がある。アラビカ種、ロブスタ種、リベリカ種だが、美味しいコーヒーは基本的にアラビカ種で、その中からさらにゲイシャ種、ティピカ種やブルボン種などに分類される。ブルーマウンテン、モカマタリという名前のコーヒーを聞いたことがあるかと思うが、これらは地名であって原種の名前ではない。 ロブスタ種はインスタントコーヒーや缶コーヒーに使われることが多く、安いが燻した香りが強い。リベリカ種は普通日本で飲むことはないだろう。私はSCAJというアジア最大のコーヒーの見本市で飲んだことがある以外では、神戸のUCCコーヒー博物館でしか見たことがない。
次に生産地について話をしよう。コーヒーベルトと呼ばれる、赤道を中心として緯度南回帰線から北回帰線の間にある熱帯地方が主なコーヒーの産地である。ただし日本でも沖縄などで少量生産されているし、実は東京の自宅でもコーヒーの木を栽培できている。去年の春に突然花が咲き、一月現在実が赤くなりつつある。

筆者宅で栽培するコーヒーの木。花はジャスミンに似た香りがした。
とはいえ、日本で生産されているコーヒーは一般流通していない。気候や風土に無理があり、収量やクオリティが商業レベルに達せられないのだと思う。 話はそれるが、ギターの木材についても状況は似ていて、和材は山桜などがギターの一部に使われるものの、ほとんどの材はアメリカやブラジルなど特定の地域から輸入されたものだ。不思議なことに、コーヒーがその土地の味を感じられるように、ギターも素材が育った風土から由来する特有の音が鳴る。
コーヒーの話に戻すが、海外では美味しいコーヒーに巡り合うことが少ない。生産国であるフィリピンやボリビアで飲んだコーヒーは苦さしか感じられなかった。これらの国では、クオリティの高いものはほとんど輸出向けに生産されているのだと思う(エチオピアやコロンビアのような、アラビカ100%生産の国なら普通のお店で飲むコーヒーも美味しいのかもしれない)。
これはコーヒーだけの話ではない。例えばチョコレートの原料であるカカオは生産地で食べることは稀であるし、近年スーパーフードとして注目を浴びているキヌアをボリビアで食べることはなかった。輸出するほうがビジネスとして有利なので、現地では流通しないのだ。