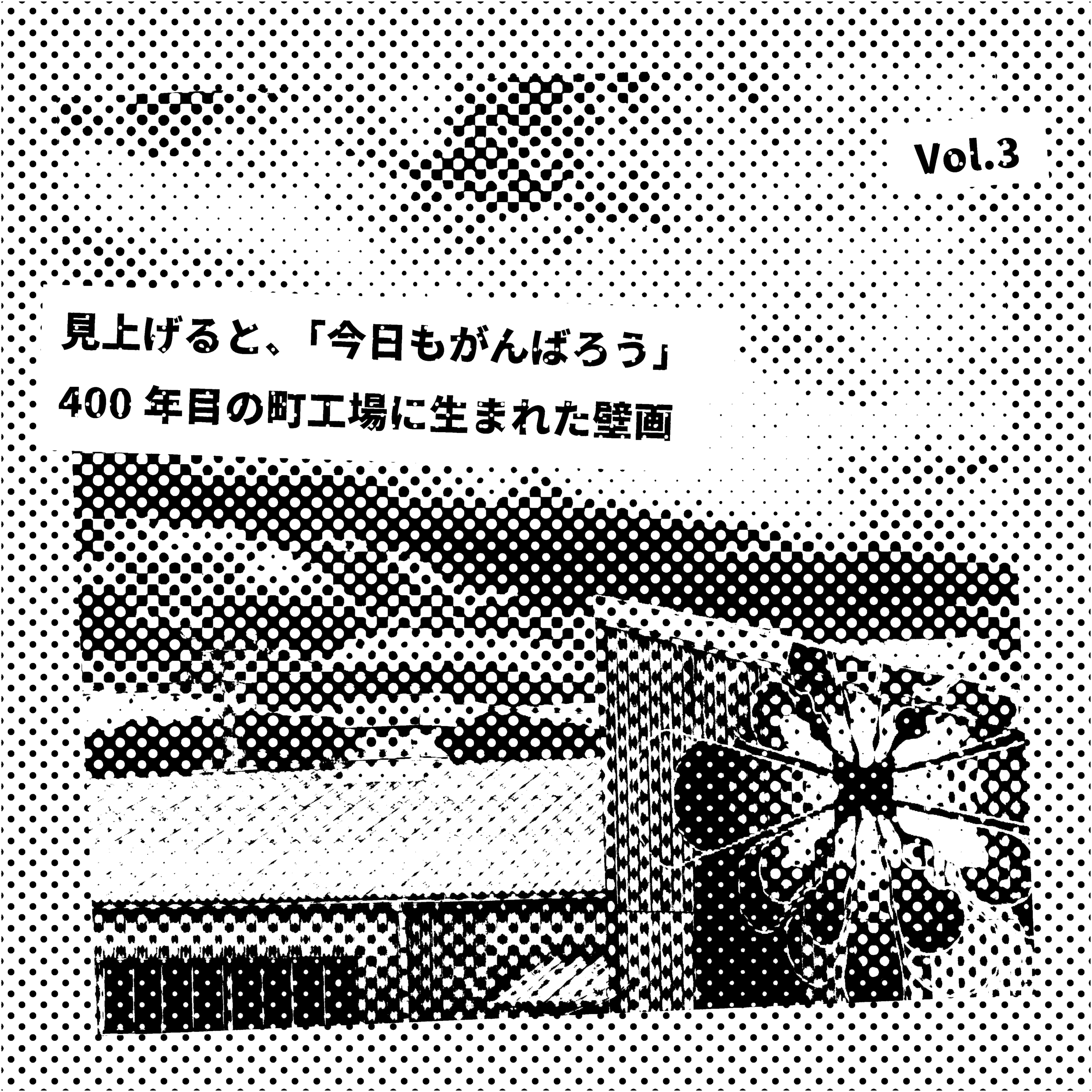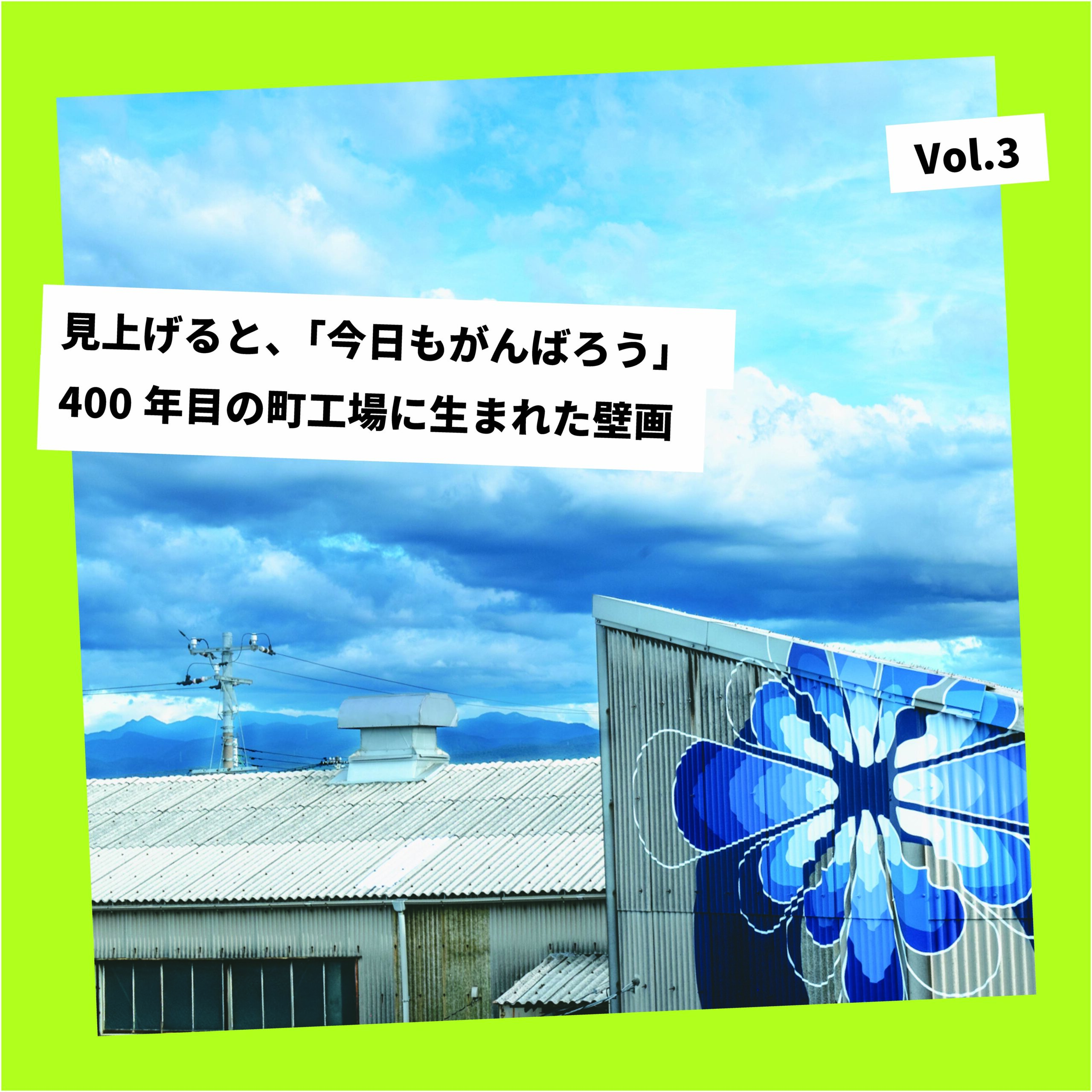洗える工芸品も開発。「ムチャ振りこそ燃える」金彩工芸士の仕事哲学
今回RE/SAUCE Projectは、岡山のサンアートでコーヒー染めを施したジャケットとTシャツを京都の金彩工芸士、三宅工芸株式会社に持ち込んで、金彩を施してもらうことに。そこで得られたのは、挑戦を続ける職人の言葉だった。
突如決めた職人としての道
古都・京都には、現在もさまざまな日本の伝統工芸が息づいている。着物に金箔を施すという特殊な技術を持つ金彩工芸士もその中のひとつだ。三宅工芸株式会社の代表であり、伝統工芸士として認定されている三宅誠己(みやけ のぶみ)さんは、38年間もの長きにわたりこの仕事に従事している職人。現在は誠己さんのほか、奥様の里美(さとみ)さん、息子で次男の大夢(ひろむ)さんの3名の分業で三宅工芸の運営を続けている。

左から次男の大夢さん、誠己さん、奥様の里美さん
三宅さんは職人でありながら、現在は自身の名を冠したNOB MIYAKEというブランドを立ち上げ、着物の打掛だけでなく、インテリアや雑貨、アパレルにアクセサリーなども手掛けている。着物というのは本来多くの職人が分業で手掛けることが普通だが、三宅工芸ではわずか3名の家内制手工業として打掛を作ることが出来る。これは極めて珍しいことなのだという。その特異性を理解するには、三宅さんの職人人生をなぞることから始めなければならない。
「僕の両親が金彩工芸士だったのですが、僕は普通に大学に行くつもりで勉強をしていました。しかし高校3年になって、急に『自分はこれから4年間も学びたいほど勉強好きではない』と気づいて、両親の職人としての仕事を継ぎたいと宣言したんです」
両親の仕事を家で間近に見ていた三宅さんは、一転して金彩工芸の道を歩むことを決意。3年間は着物の打掛を作る会社の職人見習いとして働き、その後両親と一緒に自宅の工房を手伝い始める。しかし4年働いた頃に日本経済のバブルが崩壊すると、突如両親の仕事が激減する。
「それまでは“作れば売れる”状態だった着物がパッタリと売れなくなったんです。親父から突然、『もう他で仕事を探してくれ』と言われて、3年間修行していた会社に戻ることにしたんです」
「出来ない」と言わない仕事術
三宅さんはその会社で浜崎あゆみさんや、藤原紀香さんなどセレブリティの着物の金彩を施すなど華々しく活躍。2014年に独立する形で自身の三宅工芸を立ち上げる。京都の多くの伝統産業がそうなように、着物もそれぞれ専門領域を持つ職人20人ほどが分業し、一着を仕上げていくのが通常の世界。三宅さんも金彩工芸の専門職人として活躍していたが、絢爛豪華な打掛着物の需要の低下、職人の高齢化が重なり、仕事として完成品を作ることが出来ない危機に見舞われる。
そんな状況の中で、三宅さんは本来の金彩工芸士の枠を超えた技術を習得し、全く別の業界にいた奥様の里美さんを職人としての仕事に引き込み、中学生にして「親の家業を継ぎたい」と宣言した次男の大夢さんを15歳から職人として育て上げることで、本来20人規模で作り上げる業務を、家族3人で完成させる体制を築き上げた。

真剣な眼差しで作業に向かう、大夢さん
「金彩工芸士とは名乗っていますけど、僕の職業に当てはまる言葉というのはないんです。トータルプロデュース、ディレクター、そして本来の金彩工芸、それ以外に染めも出来るし、下絵も出来るし、螺鈿も出来る。妻や息子もそうですけど、何人分もの職人の仕事を兼務しているんですよ」
伝統工芸の世界に訪れた需要低下と職人不足の危機。「全く他の仕事に就くことも頭をよぎった」というが、三宅さんはそれに抗うように自分たちの職人としての仕事の領域を増やすことで、唯一無二の存在に辿り着いた。三宅さんになぜそのように突き進むことが出来たのかを聞いてみた。
「僕はある時から『出来ません』と言うのをやめたんです。職人というのは本来、納品してはじめてお金になる仕事なので、自分が出来ないことはやらないのが普通なんです。リスクを取ることはなかなかやらない。でも僕は舞い込んできた仕事が困難なほど燃える。ムチャ振りな仕事ほどやりたくなる性分なんです(笑)」
実際三宅工芸が依頼されて生み出したものは、映画『バットマン』の世界観を金彩工芸で表現したTシャツ、絢爛豪華な金彩を施して欲しいという洋装のジャケット、それらに対して見事に答えを出してきた。
「金彩が施された着物は本来クリーニングに出すことは出来ないんです。でもジャケットならクリーニングに出せないといけない。だから研究に研究を重ねて、クリーニング可能な金彩や螺鈿を施す技法を生み出せたんです。こうした仕事は今24歳の息子が持ってきてくれることが多いのですが、『出来ないと言わない』でやってきたからこそ作れたものだと思います」
続けることにこだわり続ける
今回も東京・神宮前にオープンするカフェ「すギ留」の、コーヒー染めをしたジャケットとTシャツに金彩を施すという、着物とは全く違う依頼だったにもかかわらず、それを少しも意に介すことなく引き受けた。

奥様の里美さんが器用な手先で図案をカット。それを息子の大夢さんがシルクスクリーン版に仕上げて下地を作り、誠己さんが金彩を施して金箔の「すギ留」のロゴマークを完成させた

美しく仕上がったロゴマーク
「今回のご依頼なんて、全然ムチャ振りではないし、非常に面白かったですよ。コーヒー染めがどのような色で上がってくるのかを想像しながら、そこに何百種類もある金箔の中から合う色を提案させてもらいましたが、これもさまざまなものを作った経験が生かされていると思います」
着物の打掛だけでなく、さまざまなアイテムに挑戦している三宅工芸は、アパレルだけでなく、革やガラスなどへの金彩もやっていきたいと話す。
「いずれお話はもらえると思っていますけど、いま最もやってみたいのは、海外のメゾンブランドのバッグなどに金彩を施すことですね。そういうステージこそ日本の技術を海外に向けて発信出来るのではないかと考えています」
しかし、三宅さんはあくまでも着物を作り続けることにこだわりたいと言う。
「もし着物の需要が変わらずあったら、ずっと着物だけを作り続けていたと思います。でも今もこの先も需要は下がる一方でしょう。それでも絶対に着物作りはやめません。それを続けるために他の仕事をやっている気持ちです。僕が自分の才能を誇れるとしたら、38年間この仕事を“やめなかった”ことだと思います」
実は三宅さんはこの仕事を始めた当初から周囲には「人間国宝になる」と言い続けている。
「でもそれは“目的”じゃないんですよ。僕はこの技術をアップグレードして世界に向けて発信していきたい。その目的のためにも手段として人間国宝になるために努力を続けるんです」
【編集後記】
前例のないリクエストも「むしろ燃える」と前向きに捉えて果敢に挑戦をし、仕事の可能性を広げていく三宅誠己さん。「出来ないとは言わない」という言葉に、金彩工芸の伝統を守り、次世代に残していく覚悟を感じました。次はどんなものを生み出してくれるのか、その活躍から目を離せません。
(撮影:TAWARA、取材・執筆:武井幸久、コーディネーション:HAL.カトー)
再編集:都恋堂