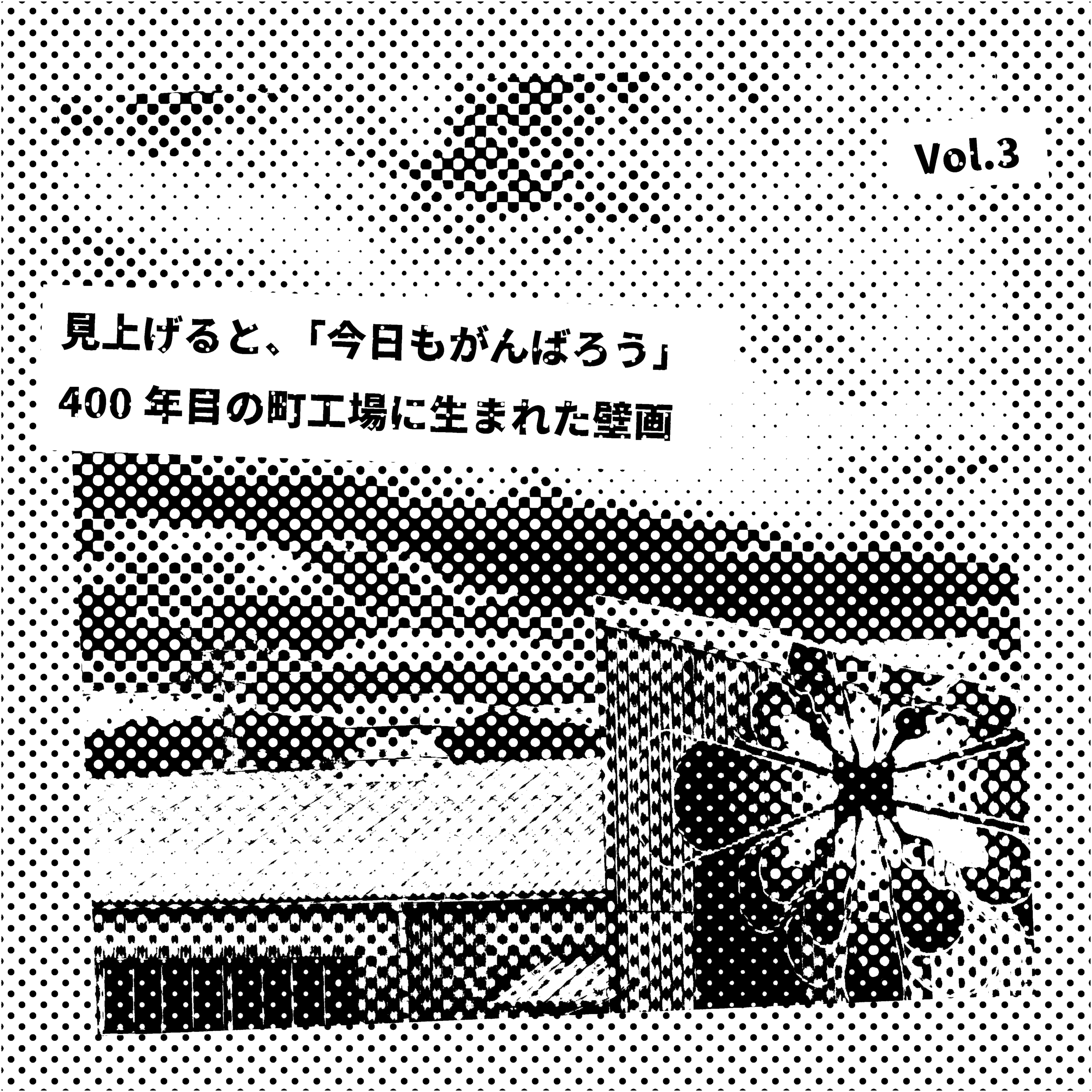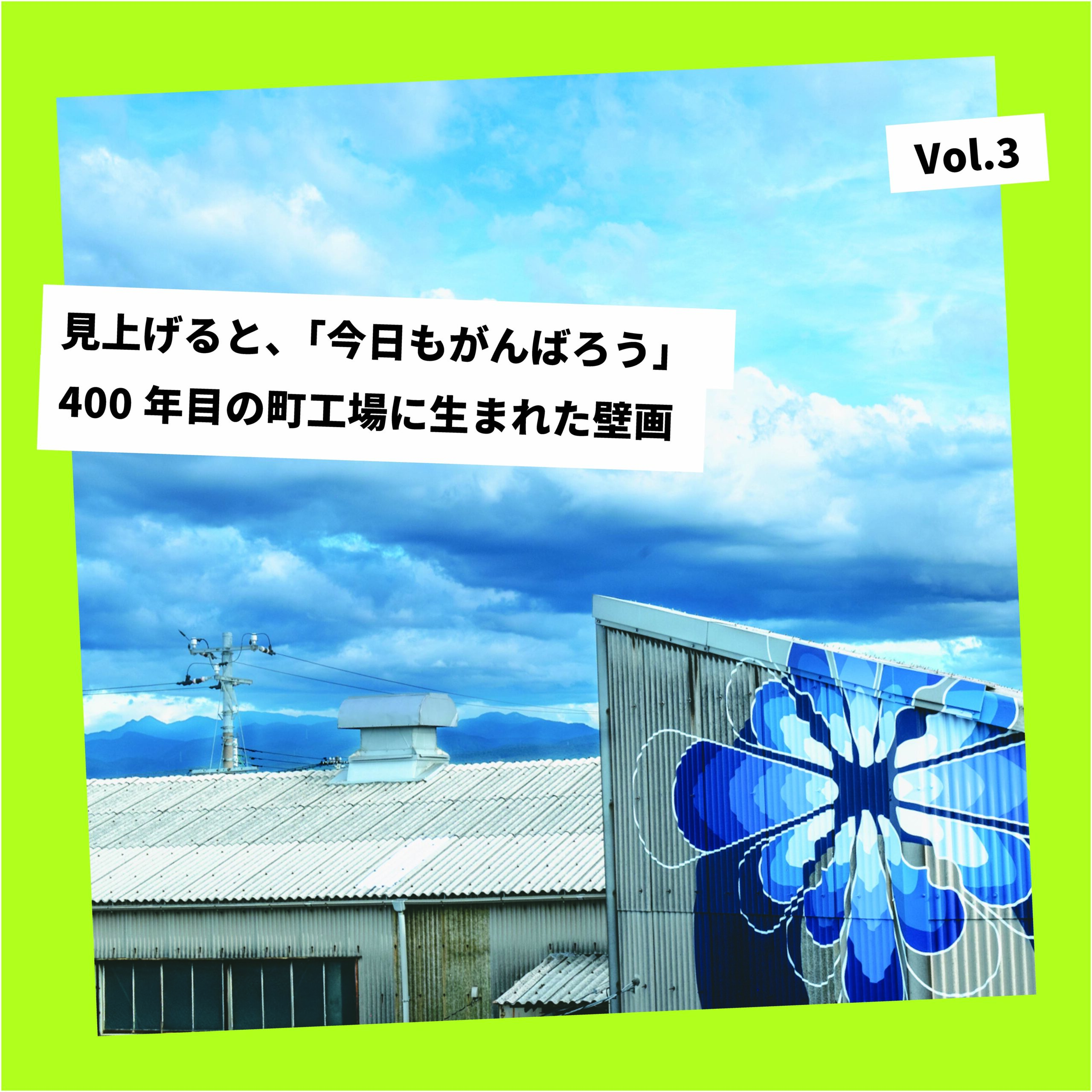オジャガデザイン・小川正をつくる6センス
第6弾は、革製品ブランド「オジャガデザイン」を手掛ける、小川 正さん。革製品の世界では“非常識”とさえされる独自製法(通称:オジャガ製法)で編み出した商品はたちまち評判を呼び、有名ブランドやキャラクターとのコラボレーションも積極的に行う。「すでに出来上がっているノウハウには頼りたくない」とゼロからオジャガ製法を作り上げる、ハングリー精神あふれるものづくりに迫った。
1. 革製品づくりの原点となった、アフリカ滞在
「10代の頃からレゲエとアフリカンミュージックが大好きで、“ジャンベ”というアフリカ発祥の太鼓を演奏してました。バイイングの仕事をしながら中南米を旅するようになって、そこで出会ったミュージシャンに教わり、ジャンベの本場であるアフリカに行くことを決意したのです。結局、通算で4年近く過ごしましたね。それから東京へ戻った後、何か仕事を始めようと思ったとき、アフリカで出会った革を使ったブランドを思いつきました。“オジャガ”というブランド名は、僕の幼少期のあだ名から取っています」

2. オリジナルにこだわるハングリー精神で好機を掴む
「正攻法でやっても勝ち目がないと分かっていたから、すでにノウハウが出来上がっているものづくりには興味が湧かなくて。ブランドはすべて独学、オリジナルで作り上げました。レザーを裁断するためには専用の用具が必要なのですが、洋服の生地を裁断するCADという機械でレザーを裁断してみたり、当時まだ一般的ではなかったPCを使ったデザインにも独学で取り組んだり。当時流行っていた裏原ブランドとのコラボをきっかけに、多くの人に知られるようになると、次はたくさん商品を作ることが課題になりました」

3. 商品の再現性を高める、機械と手縫いの合わせ技
「そこで編み出したのが、専門的な技術がない人でも製品作りができる“オジャガ製法”です。CADによるパーツの切り出しと同時に縫い穴も開ける“オジャガ製法”によって、製品の個体差が減り、再現性を高めることができました。手縫いにこだわりながらも、機械化できるところは最大限に機械化する。利用できるものなら何でも利用してみる。そういうあざとい気持ちがあったから、この製法を生み出せたのかも知れませんね。業界的には邪道と言われたこともありましたが、今があるのはこの独自製法のおかげです」

4. 専門技術は不要。雇用の幅も広がるオジャガ製法
「アパレルを含めた製造現場では、慢性的な人手不足が課題に上がっていますが、ここではその心配はありません。社内には手縫いのベテランが勤務していますが、完璧な職人技がなくても手縫いができるので、幅広い方を雇用することができています。働きたいときに働きたいだけの仕事をお願いしているので、主婦の方からも好評なんです。震災後に石巻へ出向いて、手縫いの仕事を地元の方にお願いしたこともあります。何か手を動かしていないと気持ちが塞ぎ込んでしまうという方々にとって気晴らしにもなるし、色々な状況の人と仕事を共有できるのがウチの強みでもあるのです」

5. 壮大な概念は掲げず、従業員の労働環境に向き合い続けた
「工場内では、集塵機を使い、健康被害が懸念される溶剤や染液を使わずに、レザーを染色しています。『サステナブル』や『SDGs』という言葉を頻繁に耳にするようになりましたが、オジャガデザインとしてはできることをやってきただけなんです。プロダクトを作る従業員の労働環境改善に真摯に取り組んだ結果、人手不足では困らなくなりましたね。オジャガデザインの一番腕のいい手縫い職人は、高校生の頃に職業訓練を受けてから、13年も勤続してくれています」

6. 働く人にも環境にもお客さんにも、寄り添いたい
「オジャガでは、化学物質を含むリサイクルレザーは使わず、牛とラクダの天然皮革だけを使っています。天然皮革なら土に還るし、燃やしても有害ガスが発生することもありません。どうしても出てしまう端材は、可能な限り小さなパーツに再利用しています。そうすることで、10年以上愛用して下さるお客さんの製品も、端材で作った換えのパーツでリペアが可能なんです。長く愛用してもらえれば、そのぶんお客さんとの接点も増える。そういうあざとい気持ちもあるんですが(笑)、気に入ってもらった商品を長く使っていただくことが、まず何よりも大切なのではないでしょうか」

(撮影:石井文仁、取材・執筆:川瀬拓郎、コーディネーション:峯寿之)
再編集:都恋堂