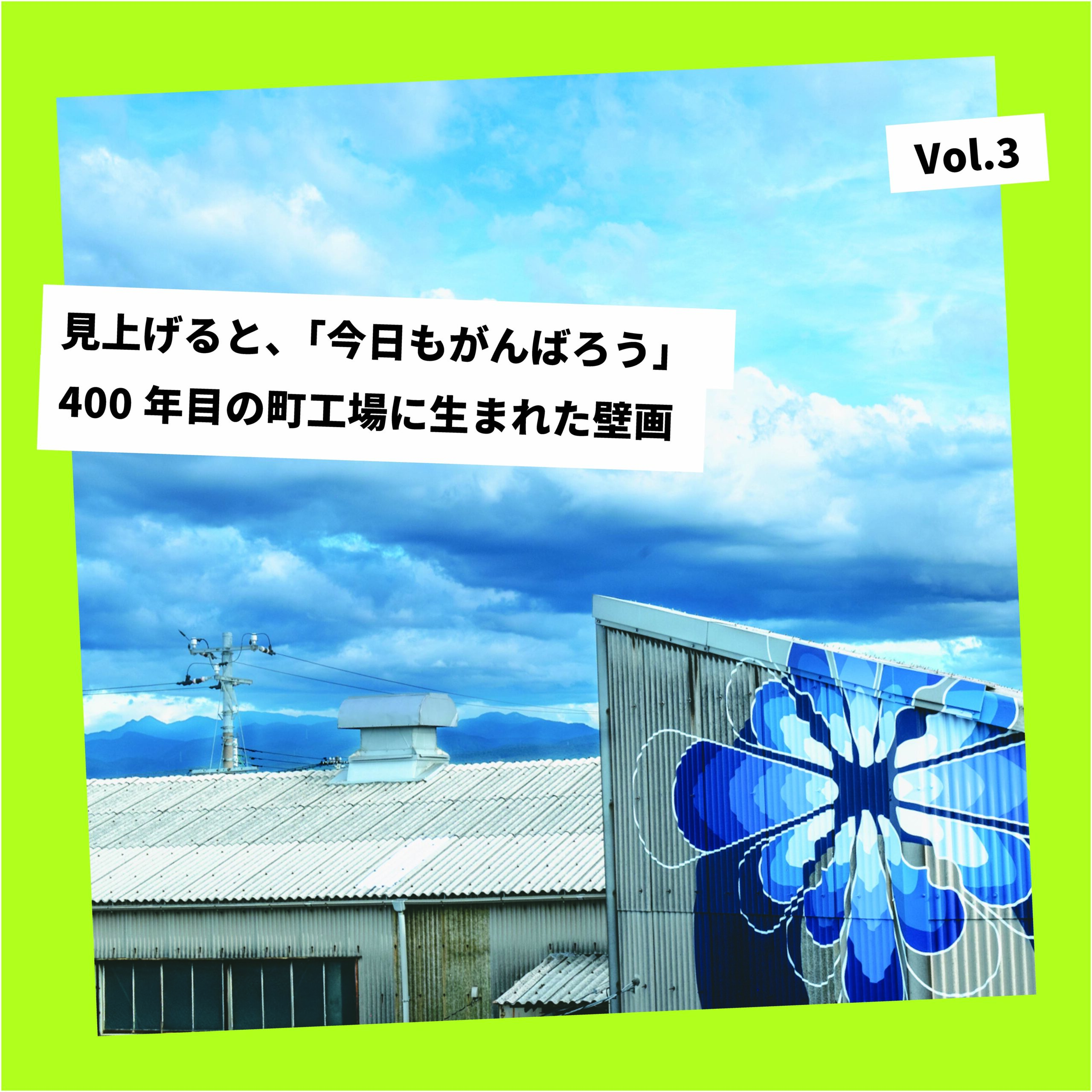R.I.P. charm・ドナルド・ムネアキをつくる6センス
第4弾は、ドナルド・ムネアキさん。奇抜なデザインや機能を兼ね備えた“ギークウォッチ”の偏愛家としても知られる彼は、廃棄寸前のジャンク品同士を組み合わせ、新たな命を吹き込むことを得意とする“改造士”。外苑前の「ワタリウム美術館」のミュージアムショップ内にある小屋型のアトリエショップ「R.I.P. STORE(アールアイピー・ストア)」では、自作のジュエリーにぬいぐるみ、80年代の時計など、ユニークなセンスあふれる作品が揃う。彼はなぜ、そしていかにして、“改造士”となったのか。その歩みをたどった。
1. “改造士”の原点は、使えないタイプライターのキー
「現在の“改造士”を名乗る前は編集者だったのですが、職業柄か、タイプライターにどハマり。最初はタイプライター文化の映像とかを作っていたのですが、全く売れませんでした。日本のタイプライター修理職人だった尾河さんという方に相談したら、『使えないタイプライターのキーがたくさん余っているから、これで何か造ってみたら?』って。そこで、キーをカフスにしたり、リングに付けたりしてDVDの付録にしたら、アホみたいに売れたんです(笑)。『これだ!』と思って、ROYAL LAZY TYPEというブランドを立ち上げました。今となれば、これが“改造士”としての始まりですね。」

2. “制作が楽しくない”。アトリエを飛び出し、ホームレスに
「ブランド立ち上げ後は、指輪やアクセサリーにカスタムして商品化もしたんですけど、だんだん作ることに楽しみを見出せなくなっちゃって。『10個オーダーが入りました』って言われて、造っていても全然楽しくなかったんです。『これが俺がやりたいことなのか?』と思っていた矢先に震災があって、ジュエリーを造る機械も壊れたのを機に、ブランドを休止しました。『改造士はじめました』とか言って。でもそこからすぐにド貧乏になって、間借りしていた千葉のアトリエからも飛び出して、そこから住所不定無職のホームレスとしての4年間が始まりました。」

3. どこまで堕ちても、やっぱり改造が好きだった
「でも、その後のホームレス生活中に働いたバーで、自作の改造グッズを販売した時に、やっぱり“改造”が好きなんだなって自覚したんです。『ここまで堕ちても自分は改造が好きなんだ』って。それから“改造士”としての活動を再開しようと、知り合いの家の駐車場に改造小屋兼ショップを建てさせてもらいました。そこに見に来てくれたのが、現在の小屋型アトリエを持たせてもらってるミュージアムショップのマネージャー・草野象さんでした。『ウチで何かやってみませんか?』と、誘ってもらって今があります。」

4. 尖った個性が詰まる“ギークウォッチ”の沼へ
「タイプライターの次にハマったのが時計。ジュエリーに組み込んだりも出来るし、改造の余地がいっぱいあると思ったんです。特に1960年代から1990年代頃までの、何かの機能に特化したもの。その頃の日本のセイコー、カシオ、シチズン、オリエントなどの時計メーカーの技術者たちは群を抜いてるんですよ。アラーム、日付、バックライト、GPSとかソーラーとか電卓とか、最先端の技術を小さな腕時計に閉じ込めるから、デザイン的にも面白いし、今見てもカッコいい。日本人の底力も感じるから、外国人の観光客にもウケがいいんです。こういう時計を“ギークウォッチ”と名付けています。」

5. 原動力は、モノが“生き返る瞬間”へのフェチに近い感覚
「時代から忘れ去られた『ジャンク』なモノに惹かれてしまうその理由が、自分でも分からないんです。引き寄せられてしまって、生理的に好きになる。もはやフェチに近いですね。一回死んだと思われるモノに愛情を注いで、『どうして世間はお前の良さが分からないんだろうねー』って可愛がってあげて、何かを造りかえて蘇らせた瞬間に“生き返った!”っていうのが分かるんですよね。モノが幸せそうなんです。」

6. 命ある限り、“シンデレラ・フィット”を追い求める
「モノをゼロから作るのって、僕にとってはロマンチックが物足りないんです。モノとモノが偶然出会って、それがピタッとハマる奇跡のマッチング。僕はそれを“シンデレラ・フィット”と呼んでいるんですけど、何かと何かが運命的にピタリとハマると、魔法がかかることがあるんです。それが例えば何かゴミとして問題になっているものでも、『こうしたらいいんじゃない?』って遊びの感覚で解決できるのが改造士としての仕事。“エコであること”なんて、スタートライン中のスタートラインですね。僕は生きている限り“シンデレラフィット”を追い求め続けるんじゃないかなと思っています。」

(撮影:TAWARA、取材・執筆・コーディネーション:武井幸久)
再編集:都恋堂